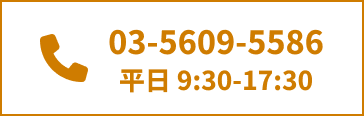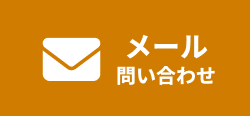よくある弁護士への相続問題のお悩みについて
遺留分侵害額請求、遺言書、遺産分割協議といった相続に関するこのようなお悩みはありませんか?
親が亡くなったが、相続人同士で話がまとまらず、遺産分割が進まない
疎遠だった兄弟が突然相続を主張してきたが、どう対応すればいいか分からない
親の預金が勝手に引き出されているようだが、取り戻すことはできるのか?
家族が認知症のため、相続手続きをスムーズに進める方法を知りたい
相続放棄を考えているが、手続きの期限や注意点を知りたい
不動産を相続したが、共有名義になってしまい、売却や管理に困っている
借金があることが判明したが、相続したくない場合の対処法を知りたい
遺産をめぐって家族が対立しているが、できるだけ円満に解決したい。
遺言書があるが、内容に納得がいかず、無効にできる可能性を知りたい
相続税の負担をできるだけ抑える方法を知りたい
相続問題について弁護士へ無料相談するメリット

相続では、遺産分割や遺言の有効性、相続放棄、遺留分侵害額請求など、多くの法律問題が関わります。また、感情的な対立に発展しやすく、家族間の関係が悪化することも少なくありません。
弁護士が第三者として介入することで、冷静かつ公平な視点で話し合いを進めることが可能になります。
相続では、遺産分割や遺言の有効性、相続放棄、遺留分侵害額請求など、多くの法律問題が関わります。また、感情的な対立に発展しやすく、家族間の関係が悪化することも少なくありません。
弁護士が第三者として介入することで、冷静かつ公平な視点で話し合いを進めることが可能になります。

相続問題の相談事例について
介護に尽くした長女の貢献を相続にどう反映させるべきか?

Aさん(長女)は、母親が亡くなる数年前から同居し、夫とともに介護に尽力していました。長年にわたり献身的に介護を続けてきたため、遺産分割の際にその点を考慮してほしいと考えています。しかし、他の相続人と意見が合わず、話し合いが進まない状況です。どのように解決すればよいのでしょうか。
本件では、長女の介護が法律上「寄与分」として評価されるかを検討しました。
具体的には、
- 介護の期間や内容
- 介護の必要性(母親の介護度)
- すでに介護に対して金銭的な補償がされていたか
これらの点を考慮し、長女の寄与分が認められる可能性について詳しくご説明しました。また、相続人全員の合意が得られれば、遺産分割協議で解決できること、話し合いが難しい場合は家庭裁判所での調停を検討する方法があることもお伝えしました。
相続人間の話し合いでは合意に至らなかったため、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てました。調停の場では、長女の介護の実績や貢献度を証拠とともに主張し、結果として寄与分が認められました。最終的に、長女の介護への貢献を考慮した適切な遺産分割が成立しました。

親の介護を担ってきた相続人が、その貢献を正当に評価してもらえないケースは少なくありません。本件のように「寄与分」が争点となる場合、法的な知識が必要になるため、専門家のサポートを受けることが重要です。相続でお困りの方は、早めに弁護士へご相談ください。
相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議の進め方
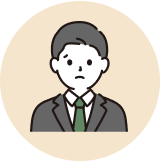
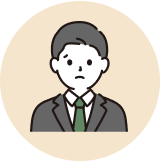
遺産相続が発生しましたが、相続人の中に介護施設で生活している高齢の方が含まれ、その方はすでに認知症と診断されています。そのため、遺産分割協議を進めようとしても意思確認が難しく、話し合いが進まない状況です。どのように対応すればよいでしょうか?
本件では、相続人の中に認知症の方がいるため、遺産分割協議を有効に進めるための「成年後見制度」の利用をご提案しました。
遺産分割協議は法律行為であり、協議に参加するためには十分な判断能力(行為能力)が必要です。そのため、他の相続人が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、選ばれた後見人が代理で遺産分割協議に参加することで、円滑な相続手続きを進めることができるとご説明しました。
家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行い、後見人が選任されました。その後、後見人が遺産分割協議に参加し、相続人全員が納得できる形で協議を進めることができました。結果として、スムーズに遺産分割が完了し、相続手続きを無事に終えることができました。



相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議が進まなくなることは珍しくありません。そのまま放置すると、相続問題が長期化し、他の相続人との関係にも影響を及ぼす可能性があります。成年後見制度を活用することで、法的に適正な手続きを進めることができますので、お困りの方は早めに弁護士にご相談ください。
借金を相続したくない…相続放棄の方法と注意点


父が亡くなり相続が発生しましたが、遺産を確認するとプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多いことが分かりました。このような場合、相続放棄ができると聞いたものの、具体的な手続きや注意点が分かりません。どのように進めればよいでしょうか?
本件では、相続放棄を行うことで借金を相続しない方法をご説明しました。相続放棄には以下の重要なポイントがあります。
- 期限がある:相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
- 一部だけ放棄することはできない:相続放棄をすると、プラスの財産も含めすべての相続権を放棄することになります。
- 次順位の相続人への影響:相続放棄をすると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移るため、事前に親族間で話し合いをすることが望ましいです。
家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行い、無事に受理されました。これにより、ご相談者様は借金の返済義務を負うことなく、安心して今後の生活を送ることができるようになりました。



借金がある場合でも、適切な手続きを踏めば相続を放棄することが可能です。ただし、期限を過ぎると借金を背負うことになってしまうため、早めの対応が重要です。相続放棄に関するご不安があれば、お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。
初回相談
0
円
あなたのお悩みを私に
聞かせてもらえませんか?
※佐々木慎平を指名の方に限り初回相談は30分無料です。 ※消費者問題と労働問題のご相談は有料相談となります。